前回のつづき。
\おさらいはこちらから/
それからの彼はと言うと、暇があれば連絡をしてきて私を繋ぎとめようと必死なように見えた。
今まで彼はきっと、私が自分のことを好きだという揺るぎない自信があったのであろう。だからあんなに私を放置したのにもかかわらずしれっと会いに来れたのだ。
けれども私は今回のことで少し引いた。「少し」というのも呆れるが。
彼は焦ったはずだ。なぜなら自分をずっと好きでいてくれる存在がいなくなるかもしれないから。究極に都合のいい女がいなくなるかもしれないから。
「俺さ、あんたといる時が一番楽しいんだよね」
私だってそうだった。そうだったのに。それなら君はどうしてあの時彼女を選んだんですかね。
「誰かと付き合いたいと思ったのまじで久しぶり」
私はてっきり付き合ってると思ってたんですけどね。確かに君からは高校生の時の彼女の話しか聞いた事はないですけどその話もはたして本当なんですかね。
もう彼の話す言葉が全部嘘のように聞こえて、素直に受け取ることができなくなってしまった。
こんな猜疑心にまみれた日々はもう嫌だ。彼のせいでもあるが、自分がだんだん嫌な女になっていくようで。
だから次会う時までには決断しなければ。これでなあなあにしてしまってはまた同じことの繰り返しだ。ここはキッパリと白黒つけてやらねば。
と強く心に決め、後日彼と会うことに。
彼は私が玄関のドアを開けるなり、突然抱きしめてきた。
「・・・なに、どうした」
驚いて半笑いになる私。
「今まで不安にさせてごめん。信じてもらえないかもしれないけど、俺やっぱりあんたのことめっちゃ好きだしずっと一緒にいたいわ・・・ねえ、彼女になってよ」
「・・・・・・・・」
彼のお得意の不意打ちとはわかっているけれど、「付き合ってよ」じゃなくて「彼女になってよ」って言ってくるところがまた憎いあんちきしょうだ。
そうだ、ここはキッパリと白黒・・・
ここはキッパリと・・・
ここは・・・
こ・・・
まだ開いたままの玄関ドアをぼんやりと眺めながら、私は返事をした。
「・・・わかった。いいよ。しょうがねえな」
彼の背中をポンポンと叩く。
「よかったー・・・」
と言いながら彼が顔をあげ、私の頬をその両手ではさむ。
彼の表情は、私の大好きなあの笑顔が少し崩れて、泣いているように見えた。
その表情を見て、私は彼のことを信じてみようと思った。
彼は私にそっとキスをし、もう一度ぎゅうっと強く抱きしめた。
玄関のドアを閉め、私たちはそのままベッドで夜を過ごした。
朝、今までと同じように彼を起こして玄関まで送り出す。
「じゃ、またね」
「うん・・・あ、そうだ。今度休みあわせてどっか行かない?あんた行きたいところとかないの?」
こんなこと言われたのは今までで初めてだ。そもそも休みなんて自由に取れないものだと思っていたし、休みがあったとしてもほぼ友人やお客さんで予定が埋まっていた人である。もしかしてそれも嘘だっ・・・いいや、彼を信じると決めたのだ。
「行きたいとこかー・・・うーん、海かなあ」
「俺も行きたいわ、海。じゃ休めそうな日連絡するからそっちも確認しといてよ」
「わかった。じゃあ今日も仕事頑張って」
「ありがと。あんたもね」
「うん。じゃあね」
はああああああ、だめだ。やっぱり負けた。あの顔を見たら勝てる気がしない。結局彼の望み通りになってしまった。
けれども今回私が少し引いたせいで彼はやっと本当に私のことを大切だって気づいたのでは?私が返事をした時のあの表情は演技ではなかったように思えた。あれがもし演技だったとしたら彼は超演技派大物俳優になれる。
とにかく私たちはもう恋人同士なのだ。私だけが付き合っていると思っていたあの虚しい関係ではない。しかも彼から付き合おうと言ってきたのだから、彼の中では私が一番好きな事には違いない。
たぶん。
・・・あ、いや、彼を信じると決めたんだった。忘れてた。
そうそう、丸1日デートなんて初めての事だ。音楽の方の予定は変えられないが、仕事の方ならばなんとでもなる。優先順位最下位だ。こんな時に仕事なんて行ってる場合ではないのだ。←
後日彼から日程の連絡があり、私も早速それに合わせて仕事を休むことにした。
アハハ。やればできるじゃないか彼。休めるんじゃん、仕事。というかさ、こんな1日デートもした事ないのに私ってばよく付き合ってるとか思い込んでたもんだわ、アホみたいだな。そうなんだよ、こういうさ、次のデートの約束ができるのが恋人同士よね。あーアホらし。笑っちゃうね。アハハハー・・・
・・・えーっと、いやいや、彼を信じると決めたのだ、私は!
そう、信じると決めた。彼を信じる。恋人として、彼のこれからを信じる。
けれど、それは早々に裏切られる事となる。
海デートの前日。夜に電話をした時、彼は出なかった。仕事遅くなってるのかなと気軽に考えて「ごめんまだ仕事だった?遅くまでお疲れ。明日何時頃にウチ来れそう?終わったら教えといてー」という内容のメールをしておいた。当日は私の家で合流して一緒に行く予定だったからだ。
だけど深夜になっても彼からの返信が無い。もうとっくに仕事は終わっているはず。仕事仲間やお客さんと飲みに行って連絡できない状況なのだろうか・・・携帯を忘れたりしてメールを見れてないとか?
まあでも仕方ない。どちらにしても明日朝には連絡がくるだろう。と思い、その日は寝た。
ところが当日、朝起きてすぐに携帯を確認しても返信はなかった。
念のため電話をするがやはり出ない。もしかして携帯を落としたのかな。それとも何か事件や事故に巻き込まれたとか・・・心配になりメールをするも返信は無い。夜遅くてまだ寝てる可能性もあるな・・・と思い、ひとまず昼までは待ってみる事にした。
が、昼になって改めて電話をしても出ない。
最終的には「もしや家でひとりで倒れてたり・・・!?」とも考えたが、そこで彼の家に押しかけるのも躊躇われた。なぜならば、私の頭の中では「家で倒れている可能性」よりも「女を連れ込んでいる可能性」の方が高いように感じてしまっていたから。信じると決めたはずだったのに、前科がチラついて行動に移せない。
だめだ、家にいると余計なことを地の果てまで考えてしまう。
そうだ、とりあえずひとりで海に行こう。行ってしまおう。もし途中で彼から連絡が来たら、海まで来てもらえば良い。
けれど、待てど暮らせど彼から連絡は来ず、まるでこれから入水しそうな暗黒の雰囲気を体全体から発しながら、私は浜辺に座ってひたすらに海を眺めていた。
その日は本当に良い天気で、もし彼と二人でここに来ていたならば一緒に海辺を手を繋いで散歩しながら沈む夕日を眺めていたのだろうなと思う。
でも私は今ひとりで夕日を眺めている。まるでこの世のありとあらゆる美しいものを全て集めたような素晴らしい夕日を。ひとりで。
何やってんだろ、私。
正直泣けた。
日も沈み、暗くなったのでそろそろ帰ろうかと思った頃に、なんと彼からついにメールが来た。
生存確認ができて安堵したが、メールを読んでそんな気持ちは吹っ飛んだ。
「連絡できなくてごめん。やっぱり付き合えない。俺と付き合ったら不幸にしちゃうから。本当にごめんなさい」
・・・・は?
ちょっと待ってよ。付き合ってって言ったのどっちだよ。それってさ、付き合ってってしつこく迫られて勢いでOKしちゃったもののよく考えたらやっぱり無理だよな〜って後悔して相手に伝える時のセリフじゃない?いや彼女になってって言われたの私のほうなんですけど?記憶喪失ですか?なんで私がフラれたみたいになってんの?おかしくない????
てかどんだけ心配したと思ってんだよ。私が心配してたのメールで見て知ってたよね?それならすぐなんでもいいから返事するべきだろ。それ伝えるのに何時間かかってるわけ?俺と付き合ったら不幸になる?なんかかっこつけてるけどそれ不幸にさせる前提で言ってません?それって自分次第よね?結局君は私のことを考えてるようで全く考えてないよね?
というかそもそもの話、そんな風に思うんだったら彼女になってとか言うな。あの流れは一体何だったの?なんなの私また夢見てたんですかね?夢オチですかね!?
相当頭にきていたが、なるべく感情的にならないように気を落ち着かせ、彼のメールに返信をした。
どれだけ心配したかということ、それならそれで前日私が連絡した時に伝えてくれたらよかったのにということ、不幸にしちゃうというのは結局君には私を幸せにしようとする気がないこと、まあそれも言い訳で今までの全てが嘘じゃないかと信用できなくなってしまったこと、君と過ごす時間は楽しかったありがとうさようならもう会わないということ。
震えた指でメールを送信し終わった時、私の中の何かが壊れた気がした。
ああ、なんだかもう疲れた。
もう彼のことは考えたくない。
なにもかもがめんどくさい。
最寄駅に着いて電車を降り、駅からの帰り道。
ぼんやりと裏通りを歩いていたら、爽やかな学生風の若者に声をかけられた。
「ねえ今帰り?・・・あれ、どしたの?泣いてる?大丈夫?」
どうやら私は泣いていたらしい。
「・・・え。いや、大丈夫なんで・・・」
「大丈夫じゃなくない?家近く?送るよ」
「いや、ほんと大丈夫だからもうほっといて・・・」
心配している風を装っているが、これは明らかにナンパだ。
「待って、大丈夫なのはわかったからとりあえずこれ使って」
と男は言ってハンカチを渡してくれた。
「・・・・うん」
と、立ち止まってハンカチで涙を拭く。
「こんな時に声かけちゃってごめんね。あ、じゃあちょっと待ってて」
「・・・・え、うん」
爽やか学生風のナンパ男はササっと紙に名前と電話番号を書いて、それを私に渡した。
「はい、よかったら話聞くからいつでも電話して。気をつけて帰ってね」
と言って、忍者のようにその場から素早く立ち去ってしまった。
「あ、ハンカチ・・・」
少し歩いたところでハンカチを返していない事に気がつき、私はすぐに紙に書いてあった「ミト」という男に電話をした。
つづく
\つづきを読む/
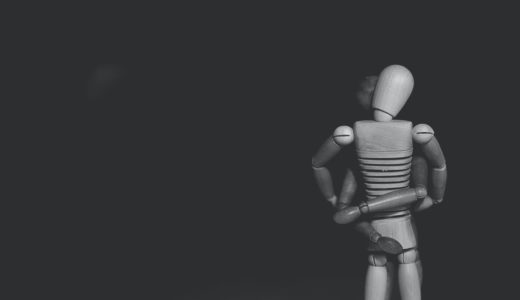 【恋愛黒歴史】雲男。その拾参
【恋愛黒歴史】雲男。その拾参



